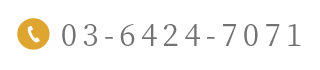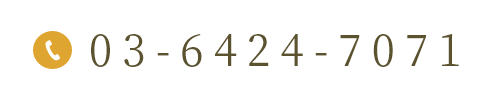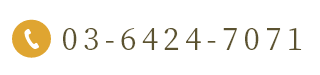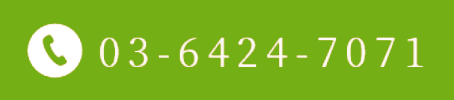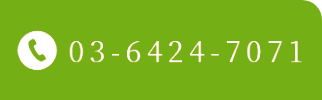国際ラドンα線臨床研究会の第2回講演会開催!「安全性」の懸念を凌駕する「有効性」視野に!
9月21日(日)には大阪市で「国際ラドンアルファ線臨床研究会」第2回講演会が開かれました。約1カ月遅れとはなりますが、そのご報告をしたいと思います。同研究会は昨年2024年から本格的な活動を開始し、本年春先に法人登記を行ない正式に発足しました。2024年10月には第1回講演会を開催し、今回はそれに続く2回目となりました。
かねてよりラドン療法(ホルミシス療法)に関しては、20年近く前から一般社団法人「ホルミシス臨床研究会」が学術活動を続けており、私もそこでの活動を通してラドン療法の理論を学び、結果として現在の「蒲田よしのクリニック」に於けるラドン療法の実践に繋がっております。
ホルミシス臨床研究会は東京など関東圏の医師が中心となって活動してきましたが、数年前から大阪や兵庫など関西圏の医師がラドン療法を取り入れる事例が増え、それを背景として「国際ラドンアルファ線臨床研究会」が大阪市で開催される運びとなりました。従って現在は2つの研究会が並立する形となっております。
同研究会は兵庫医科大学の後藤章暢教授(研究基盤教育学)が代表理事となり、医師と研究者7名が理事を務めています。毎月のようにZOOM会議の形式で理事会を開催しており、先月になり簡易版ながら研究会のホームページを開設しました。私は理事の一員であるほか、事務局を統括する任務を拝命しております。
本年4月には大阪市の会議室でリアルの理事会を行ない、今回9月の講演会に向けた本格的な準備を開始しました。前回の講演会でもスローガンとなった「人類生存のために」というテーマに関し改めて議論し、身も心も病んでいる現代人を救うために、ラドンを最大限活用しよう、という決意を新たにしました。
さて今回9月の第2回講演会には、第1回とほぼ同じ約40名の方々が参加しました。人数は同レベルですが、質疑応答の時間がオーバーするなど活発な議論が行なわれて、前回よりも大いに盛り上がった講演会となりました。地元関西が多数でしたが、東京など関東から駆け付けた一般の方も若干おりました。
講演会の冒頭では、放射線生物学者である小島周二理事(東京理科大学元教授)が、ラドンの基礎理論と安全性の検証、有効性に関する実証データなどについて講演しました。小島氏はホルミシス臨床研究会の定例講演会でも毎回のように基調講演を行なっており、私自身も多くの学びを得てきました。
続いて私を含む臨床医4名が順に講演し、有効例の症例提示のほか、有効性と安全性をどう担保するかなど臨床現場での工夫や留意点について講演しました。私はそれ以外にラドン療法を社会にどう普及するか、他の治療法との併用や医療全般に於ける位置づけなどについてもお話しました。
そしてラドンルームなどラドン関連施設を作成・運営し、研究会の立ち上げに尽力した株式会社リードアンドカンパニーの村田社長が講演会の前後に挨拶を述べ、ラドン療法を普及する事の重要性、研究会の立ち上げにかける理念と使命感などについて熱く語りました。村田氏は研究会設立の、陰の功労者といっても過言ではありません。
参加者からは鋭い質問も頂きました。ある免疫療法に関わる研究所の所長からは「ホルミシス(ラドン)の有効性に繋がる作用機序は何か」という質問がありました。作用機序に関する説明が講演にはありましたが、ラドンが有効に働くメカニズムは複雑で、全てが解明されている訳ではありません。分かりやすい解説が必要だと痛感しました。
さてラドンは放射性核種であるという事情も反映し、医学的な「有効性」と並んで「安全性」が、以前から議論の対象となってきました。放射線には「体に悪い」というイメージが先行しがちで、確かに使用法を誤ると有害となる可能性もあるのですが、安全性を担保した上で有効性を最大限に発揮する、というのが腕の見せ所といえます。
当研究会に於いても設立当初から、小島氏を中心に「有効性」と「安全性」のバランスをどう確保するか、という事が繰り返し討論されてきました。討論の詳細は省きますが、安全性を確保する上で、ラドン療法の頻度、言い換えるとラドン総量あるいは被曝放射線量をどのくらいに制限するか、が難しい線引きの論議となってきました。
この種の議論というのは、ラドンあるいは放射線による害を、どのくらい深刻と見積もるかによって、想定される結論に差が生じてきます。つまり有害な影響が無視できないとなれば、ラドン療法の回数は制限すべきという判断になりますし、あまり影響はないとなれば、ほぼ制限なくラドン療法に専念できるという判断になります。
今回の講演会を通して印象的だった事の一つは、安全性の懸念は確かにあるものの、それを遥かに上回る有効性があり、多くの疾患や体調不良、メンタル不調を顕著に改善させる力がラドン療法(ホルミシス療法)にはある、という全般的な流れが見えてきた事です。その潮流は参加者各自に伝わり、大きな反響が得られました。
安全性に関する議論は今後も継続的に必要であり、研究会では安全性のワーキンググループを結成し、定期的な会議を開いて安全性に関する研究会としてのコンセンサスを確立する事となりました。そうして得られたコンセンサスをベースとして、ラドン療法の頻度やラドン被曝量の「上限」を設定する作業へ進む事になります。
さらにラドンの「有効性」に関しては、個々の症例を積み上げる事だけでなく、研究会として「臨床研究」を計画し、実施していく方針となりました。つまり多施設に於いてラドン療法の有効性を科学的に実証し、ラドン療法を単なる民間療法ではなく、科学的にエビデンスを証明された信頼に足る治療法として確立する、という事業です。
以上のような「安全性」および「有効性」という2つの座標軸をベースとして、国際ラドンアルファ線臨床研究会では議論と活動を続けていきます。その成果は来年の第3回講演会はもちろんですが、日常的には研究会ホームページで皆様に公開していく事になりますので、ぜひその動きを注視して頂ければ幸いです。