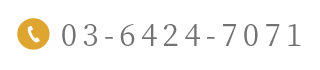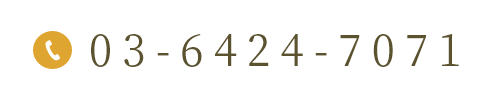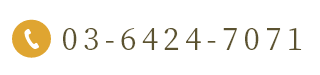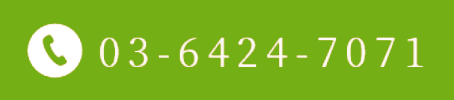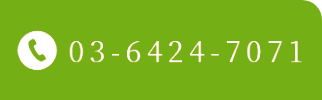心身の健康・地域医療充実・人類生存のために「ラドン」の最大限活用を!
一般社団法人「国際ラドンアルファ線臨床研究会」理事会で決意を新たに
4月6日(日)は大阪市で「国際ラドンアルファ線臨床研究会」の理事会が開かれ、そこで研究会としての活動方針が話し合われました。昨年から本格的に活動を開始した新しい研究会であり、このたび一般社団法人としての登記が完了しました。
兵庫医科大学の研究基盤教育学教授を務める後藤章暢氏が代表理事を務め、主として関西地域の医師らが中心となって結成された、ラドン療法(放射線ホルミシス療法)を研究、臨床応用、そして普及していく事を趣旨とした研究会です。
ラドン療法に関しては2007年に「ホルミシス臨床研究会」が発足し、主として関東地域の医師らが中心となり、20年近くにわたって活動を続けてきました。私自身も加入し、ラドン療法の知識と経験を深め、現在のクリニック開業に至っております。
こうした中、数年前から関西地区でもラドン療法を導入、普及する機運がにわかに高くなり、ラドン療法を取り入れる開業医が相次ぎました。そのような状況下、2024年に「国際ラドンアルファ線臨床研究会」の発足へと繋がりました。
同年10月13日(日)には同研究会の「設立記念講演会」が大阪市で開催され、研究会設立に関わった医師や関係者が一堂に集まり、様々な情報交換と活動方針の話し合いがもたれました。私も入会のうえ参加し、講演いたしました。
この設立記念講演会にはラドン療法に取り組む医師、関心のある医師や医療関係者だけでなく、一般の方々も参加され、ラドン療法に対する関心の高さがうかがえました。ホルミシス臨床研究会の流れとも合わせ、関心は年々高くなっていると感じます。
研究会は発足後まだ日が浅く、ようやく法人登記を済ませた段階です。基本的な活動方針や情報発信などのポリシーに関しては、順に固めていく方針です。私は理事の一員となったほか、代表理事などから事務局を統括する役割を任されました。
法人登記された段階で、今回の理事会開催となりましたが、そこではラドン療法をどのように医療界で広く普及していくか、ラドン療法の有効性と並んで、安全性をいかに広く伝えていくか、などについて多角的に深い議論を行ないました。
今後は定期的な理事会を行なっていくほか、私を含む事務局が各種の取りまとめや情報発信を行ない、研究会としての活動を展開していきます。具体的な決定事項として、一つには9月21日に年次の講演会を開催する事が決まりました。
「国際ラドンアルファ線臨床研究会」の活動に関しては、当ブログでも随時お伝えしていきます。「蒲田よしのクリニック」でもラドン温浴療法を中心に、同研究会の活動と連動する形で、診療および研究、普及活動を進めていく事になりそうです。
昨年10月に開催した「設立記念講演会」のパンフレット表紙には「人類生存のために・・(中略)・・低線量放射線ラドンアルファ線療法」という標題が掲載されています。「人類生存」というと大げさな感じもしますが、決して大げさな事ではありません。
次回以降は数回にわたり、ラドンが病気の治療や予防、心身の健康に寄与するだけでなく、地域医療の充実、さらには人類の生存にも深く関わるという事に関して、私の臨床経験や他研究会での活動とも関連づけてお話しようと考えております。
・・(続く)
うつゼロドットコム YouTubeページ
https://www.youtube.com/@%E3%81%86%E3%81%A4%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%83%89%E