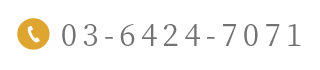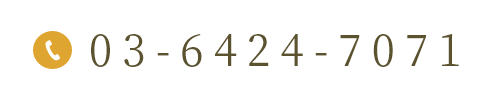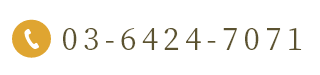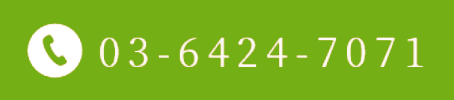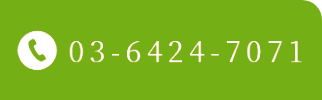ノーべル賞受賞・坂口氏の研究「制御性T細胞」・・実は「ラドン」が活性化していた!?
ノーベル生理学・医学賞を受賞する坂口教授らが設立したレグセル社が、2026年にも米国で初の臨床試験(治験)を始める予定、と報道されました。自己免疫疾患が対象で、坂口氏らが発見した「制御性T細胞」を用いた治療薬の開発を目指すものです。
坂口氏が発見した制御性T細胞は過剰な免疫の働きを制御する役割を持ち、免疫が体内の正常な細胞を攻撃することで発症する関節リウマチなど、各種の自己免疫疾患などの治療につながると期待されています。
実際に対象患者へ投与するのは、患者自身から取り出した通常の性質を持つ免疫細胞を、特殊な培養法などで性質を改変した、いわば人工的な制御性T細胞です。体内の制御性T細胞は量が少なく治療に使いづらかったのですが、体外で人工的に作ったものを患者に投与して補えば、十分な治療効果が期待できると説明されています。
治験は「フェーズ1」から始まって「フェーズ3」まで段階的に進みますが、治験の開始から承認されるまでに通常5〜8年はかかるとされており、実用化は2030年以降になりそうです。
このようなノーベル賞受賞を契機とした治験の動きよりも先行して、実はラドン療法(アルファ線およびガンマ線)により「制御性T細胞」の誘導が証明された、という画期的な研究があります。東京理科大学元教授で放射線生物学者である小島周二氏による「低線量ガンマ線照射による制御性T細胞の誘導と自己免疫疾患の改善」です。
かなり以前からラドン療法に取り組む医師からは、全身性エリテマトーデス(SLE)、関節リウマチ(RA)などの自己免疫疾患に対するラドン療法の有効性が多数報告されてきましたが、小島氏らは低線量ガンマ線照射の効果を、それぞれのマウスモデルを用いて検討してきました。
これらの実験では、マウスに500 mGyのガンマ線を週5回、4週間全身照射しましたが、その結果、これらの疾患は低線量ガンマ線照射によって症状が改善すること、またそのメカニズムに制御性T細胞(Treg)が関与していることが証明されました。
この研究と関連して、小島氏がラドン療法の有効症例を提示し、Tregとの深い関連性に言及した医学論文を以下に紹介いたします。
https://radon-clinical.org/wp-content/uploads/2025/09/Ref.-4.-Eng.pdf
さて、ここ数年とりわけ問題となっている健康問題として、コロナ感染後およびコロナワクチン接種後に多発している筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群(ME/CFS)があります。これは感染後や接種後の様々なタイミングで倦怠感、ブレインフォグ(思考力などの低下)、うつ症状、不眠、起立性障害、全身の筋肉痛などの多彩な症状に見舞われる、治療法が確立していない疾患です。
このME/CFSでは病態の一つとして、神経接続部などに於ける「慢性炎症」が知られています。神経接合部にはセロトニンやアドレナリン、アセチルコリンなど神経伝達物質の受容体が存在し、様々な情報伝達が行なわれていますが、その慢性炎症により倦怠感、ブレインフォグ、うつ症状、不眠、各種の自律神経失調症状が引き起こされます。
実はこのME/CFSに、ラドン療法がたいへん有効である事が知られてきました。病院の検査では原因が分からず、治療法もないと言われた多くの方々が私の「蒲田よしのクリニック」などに来院し、栄養解析などの検査を受けた上でラドン療法(ラドンルーム)に取り組みましたが、大半の方々で症状が明らかに軽減しました。
ME/CFSに対するラドン療法で、前述のTregが誘導されているかどうかの検討は今後の課題ですが、慢性炎症が関係しているのは確実であり、ラドン療法により慢性炎症が沈静化していると推測されるため、恐らくTregに対してもポジティブな影響が加わっているのではないかと考えられます。
さてコロナ感染後およびコロナワクチン接種後のME/CFSに対しては、ビタミンD補充療法の臨床研究が進行中であり、中間集計では極めて良好な結果が得られました。ME/CFSに対する有効な治療法の一つとして確立される可能性がありますが、これにラドン療法を併用すると、さらに優れた臨床効果が得られることが期待されます。
冒頭で紹介したような、特殊な技術を駆使して作成した「人工的な制御性T細胞」の臨床研究も期待されますが、膨大な費用と10年近くもの年月を要し、研究も上手くいくとは限りません。それを待つだけでなく、有効性が証明されつつあるビタミンDやラドン療法に取り組むのも、現実的で可能性の高いアプローチではないかと考えております。