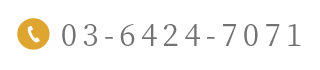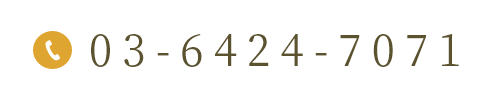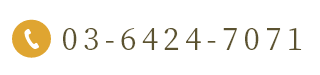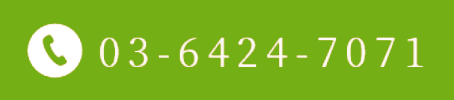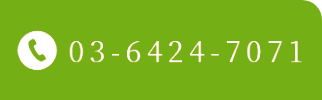国際ラドンアルファ線臨床研・第2回講演会2025年9月21日・講演抄録原稿
(国際ラドンアルファ線臨床研・第2回講演会2025年9月21日・講演抄録原稿)
心身の健康・地域医療充実・人類生存のために「ラドン」の最大限活用を
蒲田よしのクリニック 吉野 真人
私が経営する東京都大田区「蒲田よしのクリニック」では2011年の開業以来、(株)リードアンドカンパニー社が制作したラドンルームを併設し、漢方療法や栄養療法、プラセンタ注射、点滴療法などと組み合わせる形でラドン温浴(放射線ホルミシス療法)にも取り組んでいる。
クリニック開業以来14年近くにわたり、ラドン温浴を始めとする治療法の幅広い有効性が好評であり、更年期障害に悩む40~50代女性を主体として、慢性疲労や不眠、不安神経症、うつ状態などメンタル不調、自律神経失調症、各種ガンなどの患者が多数、訪れてきている。
例えばメンタル不調の方々の多くは精神科、あるいは心療内科などで主に薬物療法を受けているが、治療薬の効果が不充分、あるいは副作用に見舞われ、他の治療法に活路を見出すため、内科クリニックであるにも関わらず、当院へやって来るのが実情である。
慢性疲労やメンタル不調、自律神経失調症などの症例の多くでは鉄欠乏、ビタミンB群欠乏、ビタミンD欠乏、タンパク質代謝障害など「栄養バランスの乱れ」や「代謝異常」が明らかに認められる。そのような状況下、当院では栄養療法にとりわけ力を入れている。
栄養療法と並んで有効性が高いのが「ラドン療法」である。上記のような栄養バランス失調や代謝障害の症例では多くの場合「腸内環境」の乱れが影響している。従って代謝や腸内環境の改善が求められるが、これらに対しラドン療法はたいへん有効である。
一方、ガンセンターや一般病院で治療に難渋する進行がんの方々も散発的に来院されているが、高濃度ビタミン点滴などと組み合わせる形でラドン温浴に取り組み、主要の縮小やQOL(生活の質)向上などの形で、総じて良好な治療効果が得られている。
がん患者の多くは病院で手術、抗がん剤投与、放射線照射などの「標準治療」を受けているが、大半がその「副作用」に悩まされている。例えば抗がん剤では強い吐き気に見舞われるが、ラドン温浴はその辛い副作用を強力に緩和し、患者のQOL向上に寄与している。
さて2020年からの新型コロナウイルス感染の流行、それに対応するコロナワクチン接種の推進に続き、全身倦怠感や不眠、めまい、思考力低下などのブレインフォグ、呼吸苦、動悸、全身の筋肉痛・・など極めて多彩かつ複雑な症状を訴える方々が急増している。
そのようなコロナワクチン接種に起因する複雑な体調不良、いわゆる「ワクチン後遺症(PVS)」の患者が多数発生し、蒲田よしのクリニックへも概算で数百名が来院してきた。コロナ感染症に引き続く「コロナ後遺症」と並んで、たいへん深刻かつ重要な医学的課題となっている。
ワクチン後遺症は、政府が積極的な対策を取らず、公正な報道がなされない事も影響し、適切な診療を受けられない患者が滞留しているが、「全国有志医師の会」および「ワクチン問題研究会」などの団体が、一致協力して治療法の研究および情報共有に取り組んでいる。
コロナ後遺症およびワクチン後遺症に関しては、世界中で同じような問題に直面しており、主要症状に関して「筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群(ME/CFS)」という疾患概念が多くの専門家により提唱され、病態解明と治療法の研究が俄かに進んできている。
ME/CFSに対しては様々な治療法が試され、個別の症例では有効例も決して少なくないが、臨床試験を通して有効性が実証された治療法は多くない。例えばグルタチオン点滴がME/CFSに有効、という報告は多いが、臨床試験によって証明された訳ではない。
そうした状況下、ワクチン問題研究会がME/CFS症例ではビタミンD血中濃度が著しく低い事に着目し、ビタミンD補充療法を実施したところ、多くの症例でME/CFS症状の軽減が認められた。現在その有効性を実証するランダム化比較試験が進行中である。
一方、当院では多くのME/CFS症例に対して、栄養療法や点滴療法などと並行してラドン温浴を施行し、多くの有効症例が出ている。統計的な検討は今後の課題であるが、ラドン温浴を行なった症例の9割以上では明らかな体調の改善が得られている。
以上のようにME/CFSに象徴される、多彩かつ複雑な症状および病態の疾患や体調不良に対し、薬物療法に代表される従来の西洋医学が限界を迎えているのは明らかである。その限界を打破する画期的な治療法の一つが、ラドン療法であると考えられる。
そのように、ME/CFSや各種ガンなど多くの疾患や体調不良に対して有効性の高いラドン療法を、どのようにして広く普及していき、一人でも多くの方々がその恩恵に浴することが出来るようにするかが、当研究会に関わる今後の重要な課題の一つである。
さてラドン温浴療法(放射線ホルミシス療法)を広く普及するための手段は、以下の4つに大別されると考えている。
1:個々のクリニックで集患促進
ラドンルームまたはレスピロ等の設備を備えた病院や個人クリニックが、独自の戦略で集患(患者の来院・受診を促すこと)することを通して、各々の地域にラドン療法を普及していく方法。医療機関ホームページやブログ、動画、SNSなどの活用も推奨される。
これが最も基本的な戦略であるが、えてして医師個人の力量とエリアに限定される。つまり個々の医師や医療機関スタッフの実力や治療メニュー、適応疾患に関わる患者数の多寡などの条件に左右され、また医療機関の所在するエリアに拘束される限界がある。
2:ラドン導入医療機関を増やす
全国の病院や個人クリニックに、ラドンルームやレスピロ等の設備を普及していくという戦略である。これらの設備が広範囲に普及していけば、施設に通ってラドン療法を受け、疾患や体調不良の根本的な治療を受けられる患者が、施設数に比例して増えていく。
この場合、医師をはじめとする医療専門職に向けた、ラドン療法に関する情報発信、およびラドン療法に関心のある医師などへのフォローアップが重要である。またこのシナリオでは、ルーム等に使用する「ラジウム鉱石」の供給量そのものが制限要因となる。
3:病診連携し病院から患者紹介
各ラドン併設医療機関のエリアごとに地域の一般病院やクリニックと連携し、病院等で精密検査や鑑別診断の済んだ慢性疾患や慢性疲労症候群などの患者を、ラドン療法を含む総合的な治療を目的として、ラドン併設の医療機関へ紹介する取り組みである。
このような形態の患者紹介が進めば、一般病院などに滞留している多くのME/CFSをはじめとする難治性の疾患や体調不良の患者が、スムーズにラドン療法を受ける道筋が出来る。このような患者の流れは、新たな「病診連携」となり得る価値のあるものである。
但しこのような「新型病診連携」は、一般病院や医師会、あるいは地域の行政などの理解を得て、組織的な協力を得る必要がある。薬物療法や西洋医学中心の一般病院や医師にとってハードルの高い連携ではあるが、根気強く取り組む必要のある事業である。
4:企業オフィス等で設置し共用
各ラドン併設医療機関のエリアごとに企業と契約し、企業の社員向けにラドンを活用したサービスを行なう。例えば企業オフィスの各フロアにラドンボールを入れたホットを用意し、フロアの社員や来客などが自由に「ラドン水」を飲用する事が出来るようにする。
あるいは必要枚数の「ラドンマット」を用意しておき、時間ごとに希望する社員などへ貸与するのも良いアイデアである。企業の財務状況が許せば、オフィス内に小さいラドンルームを併設する事も選択肢に入り得る。ラドンルームは社員のほか来客なども利用できる。
このような企業や職場の取り組みにより、社員の心身にわたる健康増進や各種の疾病を予防する事はもちろん、業務効率の改善、欠勤率や離職率の低下、生産性の向上などにも繋がり得る。これは経産省が推進する「健康経営」の趣旨にもかなうものである。